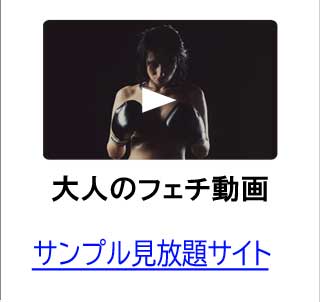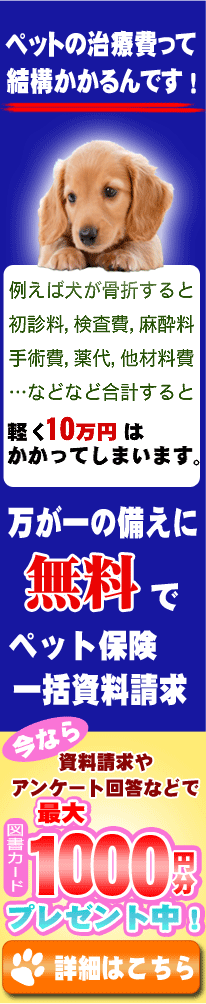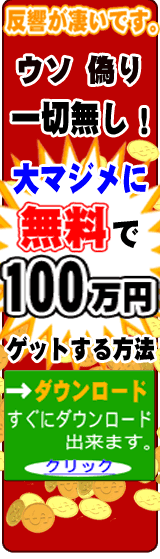"山城しんごの城めぐり 県指定史跡 猪苗代城(福島県猪苗代町)" の動画はこちら
|
この動画をTwitterで共有! |
外部プレーヤー埋め込みタグ |
"山城しんごの城めぐり 県指定史跡 猪苗代城(福島県猪苗代町)"のニコニコ動画詳細情報
山城しんごの城めぐり 県指定史跡 猪苗代城(福島県猪苗代町)
山城しんごの城めぐり 県指定史跡 猪苗代城(福島県猪苗代町)

Wikipediaより文治5年(1189年)の奥州合戦での戦功により、佐原義連は会津4郡を与えられた。その子・盛連の長男・大炊助経連は耶麻郡猪苗代を領して、猪苗代氏を称したと伝えられる。経連は、宝治2年(1248年)3月、将軍・藤原頼嗣に仕え、会津猪苗代麻谷庄5000余町を与えられ、猪苗代氏を称したという。建久2年(1191年)、佐原経連が猪苗代八手山城を築き、亀ヶ城と称したとしている。しかし、『新編会津風土記』では、八手山館は白津の東北東の根岸山というところにあったとしており、『猪苗代町史』では、猪苗代城(亀ヶ城)と八手山館は別個のものとしている。築城時期も、宝治元年(1247年)の宝治合戦以降とみるべきと指摘している。会津盆地を治めていた蘆名氏も佐原義連の血統で、猪苗代氏とは同族である。猪苗代氏は本家・蘆名氏に対しては、反逆と従属を何度も繰り返し、最終的には、天正17年(1589年)の摺上原の戦いの直前に、当時の当主・猪苗代盛国が伊達政宗に内応し、蘆名氏を滅亡に追い込むこととなった。豊臣秀吉の奥州仕置によって伊達氏が会津を離れると、盛国も猪苗代を離れ、約400年に及ぶ猪苗代氏の支配が終焉した。その後、会津領主は蒲生氏郷、上杉景勝、蒲生秀行、蒲生忠郷、加藤嘉明、加藤明成と続く。猪苗代城は会津領の重要拠点として、江戸幕府の一国一城令発布の際もその例外として存続が認められ、それぞれの家中の有力家臣が城代として差し置かれていた。蒲生氏郷のとき、同城には蒲生郷安が入った。九戸の乱の平定後、同城には、玉井貞右が入った。慶長3年(1598年)1月、上杉景勝が会津に移封されると、同5年(1600年)春、今井源右衛門国広(または国清)が同城に入るが死去[8]。後任として水原親憲が福島城から移った。関ヶ原の戦い後、蒲生秀行が再入部すると、猪...
動画ID:sm44875950
再生時間:22:20
再生回数:再生回数: 回
コメント数:0
マイリスト数:1
最新のコメント:
タグ:城,,