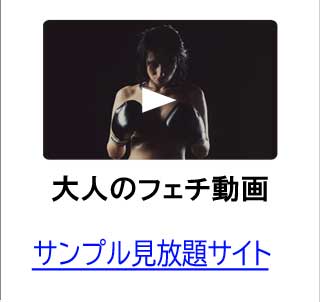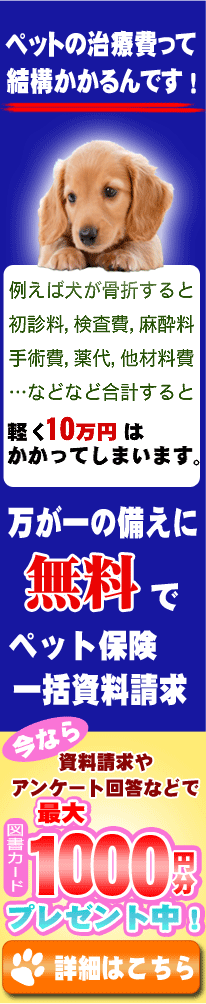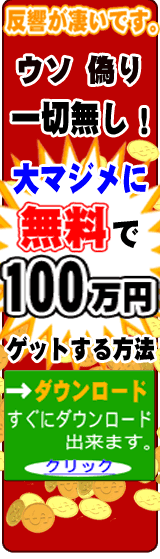"山城しんごの城めぐり 国指定史跡 鶴ヶ岡城(山形県鶴岡市)" の動画はこちら
|
この動画をTwitterで共有! |
外部プレーヤー埋め込みタグ |
"山城しんごの城めぐり 国指定史跡 鶴ヶ岡城(山形県鶴岡市)"のニコニコ動画詳細情報
山城しんごの城めぐり 国指定史跡 鶴ヶ岡城(山形県鶴岡市)
山城しんごの城めぐり 国指定史跡 鶴ヶ岡城(山形県鶴岡市)

Wikipediaより慶長5年(1600年)関ヶ原の戦いの後、上杉氏は西軍に加担した罪により会津120万石から米沢30万石に減封され、代わって庄内地方を支配したのは山形城を本城とする最上義光である。義光は24万石から57万石を領有する大大名となった。義光は庄内地方の拠点として大宝寺城、東禅寺城、尾浦城などを整備拡張した。慶長8年(1603年)各城の整備が整うと、酒田浜に大亀が上がったことを祝し東禅寺城を亀ヶ崎城と改称した。この時に、亀ヶ崎に対し大宝寺城も鶴ヶ岡城と改称されたのである。また同時に尾浦城も大山城と改称された。最上氏は3代義俊の元和8年(1622年)に、お家騒動(最上騒動)があり、改易となった。旧最上領は分割され、庄内地方には信濃国松代城より譜代大名の酒井忠勝が入った。忠勝は鶴ヶ岡城を本城と定め、亀ヶ崎城を支城とした。忠勝は入封すると、簡素な造りであった鶴ヶ岡城を近世城郭へと大改修に着手した。二の丸、三の丸を拡充し、城下町の整備を行った。庄内藩の本城としての偉容が完成したのは、3代忠義の時であり54年の歳月が費やされた。本丸は一部に石垣が使用されたが大半が土塁であり、幅約20mの水堀に囲まれている。本丸内には御殿と北西隅の二重櫓が天守代用としてあり、他に単層2階の他門櫓が2基上がり本丸の城門は櫓門が上がっていた。二の丸東南隅に2重櫓、二の丸の城門も全て櫓門であった。宝永元年(1704年)には、鬼門である東北隅に稲荷神社が勧進され、毎年の初午祭礼の際には町人も城内に入って参詣することができた。文化2年(1805年)、9代忠徳は藩校「致道館」を設けた。文化13年(1816年)には現在地である三の丸に移転された。文政7年(1824年)、柿葺であった城内の建物は、全て瓦葺となった。天保11年(1840年)幕府より三方所替の命が下り、酒井氏...
動画ID:sm44877732
再生時間:38:07
再生回数:再生回数: 回
コメント数:0
マイリスト数:0
最新のコメント:
タグ:城,,