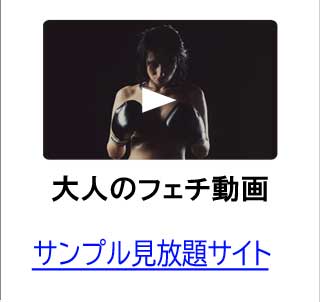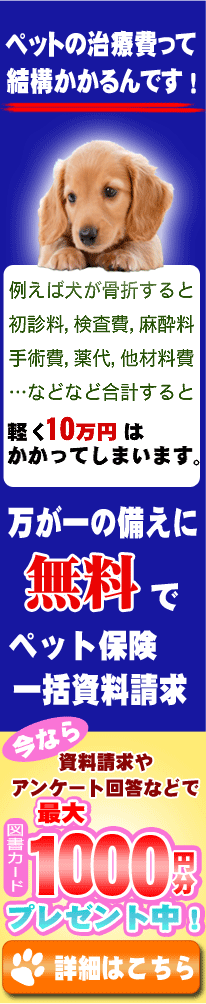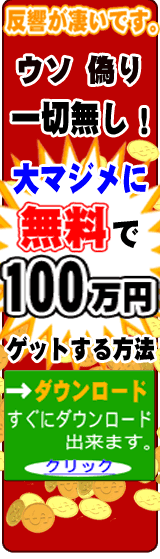"ukiyojingu+結月ゆかり『非在都市のサウンドスケープ、或いは存在の境界を彷徨う幽霊たちのための記憶..." の動画はこちら
|
この動画をTwitterで共有! |
外部プレーヤー埋め込みタグ |
"ukiyojingu+結月ゆかり『非在都市のサウンドスケープ、或いは存在の境界を彷徨う幽霊たちのための記憶..."のニコニコ動画詳細情報
ukiyojingu+結月ゆかり『非在都市のサウンドスケープ、或いは存在の境界を彷徨う幽霊たちのための記憶...
ukiyojingu+結月ゆかり『非在都市のサウンドスケープ、或いは存在の境界を彷徨う幽霊たちのための記憶...
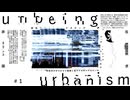
非在探求#1解説:https://note.com/ukiyojingu/n/nf886f214db7d?sub_rt=share_pw合成音声音楽は本質的にアルゴリズム的存在であり、その自動生成的な特性は、生成AIによる音楽と本質的に地続きでないだろうか。そうした問題意識から、筆者は「純粋合成音声音楽」という言葉に辿り着いた。人間の手がどれほど介入しているかの程度はあるとはいえ、ボーカロイド音楽も生成AIも規定されたパラメータに依拠しており、自由に見えるその創作もまた、制御された構造だ。ゆえに、全ての音を人間の意図から解放し、アルゴリズムの論理だけで構成する音楽は、合成音声音楽の本質をより鋭く露呈させるものではないだろうか。だがそのような方向性は、筆者がこれまで展開してきた思想とどこか相容れないようにも映る。筆者はかつて、情報に満ちた都市空間を「構造」と見なし、それに絡め取られず逃れる線として「海辺」という概念を提示してきた。都市の過剰なスクリーン、強制的な固有化、情動の巻き込みといった構造に対抗するには、どちらにも属さない中間地帯=「海辺」が必要なのだと。そこでは一貫した立場を取らず、むしろ「幽霊」のように輪郭を曖昧にした存在であることが、構造からの抵抗線となる。この立場から見ると、「純粋合成音声音楽」は構造に寄り添う方向、すなわち都市構造と同質のアルゴリズム的環境に身を置く試みに見える。だが筆者は、そうした矛盾を否定するのではなく、それを孕んだまま思考を進める。完全に人間が不在となるような音楽を構想することは、逆に人間性を再浮上させる契機になりうるのではないか。つまり、幽霊的な立場を保ったまま、非在を通じて創造性を再定義するのである。マリー・シェーファーのサウンドスケープ論を補助線に用いるのはこのためである。サウンドスケープとは、...
動画ID:sm45226645
再生時間:5:33
再生回数:再生回数: 回
コメント数:13
マイリスト数:18
最新のコメント:うぽつ どうにも、どこか... うぽつです! noteも読みました... 非在都市のサウン... 8888888888 無機質の美 うぽつです!!...
タグ:ukiyojingu,POEMLOID,ポエトリーリーディング