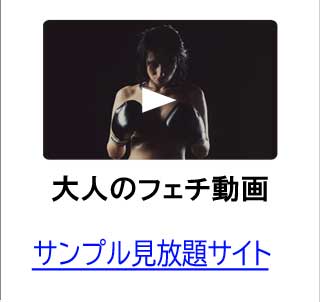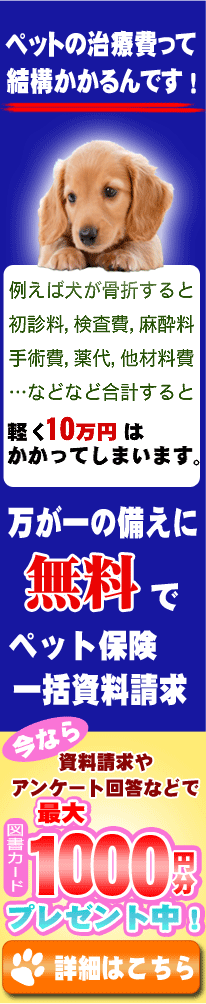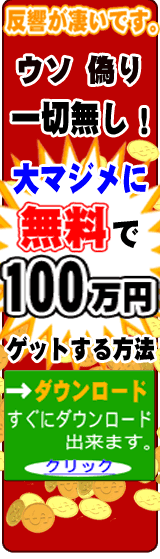"【DTM】前奏曲、フーガとコラール(1872)(J.S.バッハ 作曲、J.J.アーベルト 作編曲)【A=432Hz】" の動画はこちら
|
この動画をTwitterで共有! |
外部プレーヤー埋め込みタグ |
"【DTM】前奏曲、フーガとコラール(1872)(J.S.バッハ 作曲、J.J.アーベルト 作編曲)【A=432Hz】"のニコニコ動画詳細情報
【DTM】前奏曲、フーガとコラール(1872)(J.S.バッハ 作曲、J.J.アーベルト 作編曲)【A=432Hz】
【DTM】前奏曲、フーガとコラール(1872)(J.S.バッハ 作曲、J.J.アーベルト 作編曲)【A=432Hz】
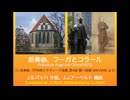
ボヘミア出身でドイツで活躍した作曲家、ヨハン・ヨーゼフ・アーベルト(Johann Joseph Abert 1832-1915)が、バッハ(J.S.Bach 1685-1750)の2作品を自身のコラールで結合させてまとめた音楽を、打ち込みで再現してみました。(どういう経緯でこの作品にたどり着いたのか、思い出せませんw)この曲は、以下の3曲で構成されます。管弦楽編曲は、全てJ.J.アーベルトです。(1) 前奏曲(平均律クラヴィーア曲集 第4曲 嬰ハ短調 BWV849 より)Andante(2) コラール(J.J.アーベルト作曲)Grave(3) フーガ(幻想曲とフーガ ト短調 BWV542 より)Allagro non troppo(1)の原調は嬰ハ短調ですが、二短調で編曲されています。(2)(3)はト短調で、切れ目なく演奏されます。(2)で登場した旋律が、(3)の中にも登場し、初めは控えめに出てきますが、終盤では主役を張りますw「グノーが『アベ・マリア』でやったこと*を、管弦楽でやってみた」って感じです。(それにしても、2曲で構成される各曲から、(1)と(3)をピックアップした理由が、よくわかりません。BWV542の管弦楽化は、複数の音楽家が行っています。)(*フランスの作曲家シャルル・グノー(1818-1893)は、バッハの前奏曲(BWV846)の上に、自身の作曲した旋律を乗せて作品にしました。)そもそも、アーベルトがどうしてこういう音楽を作ろうとしたのか…等々、曲について少し調べましたが、「1876年にアメリカ初演」ぐらいしか分かりませんでした。(楽器編成)二管編成Fl2, Ob2, B管Cl2, Fg2, F管Hrn4, B管Tp2, Tb3, Timpani, 弦5部アーベルトは交響曲7曲、オペラ5曲以上などを作曲していますが、現在はあまり演奏されていないようです。自身の楽器でもあったコントラバス関連の作品も、多数作曲しています。この曲は別の作曲家によって、吹奏楽にも編曲されています。興味のあ...
動画ID:sm45313970
再生時間:12:38
再生回数:再生回数: 回
コメント数:1
マイリスト数:0
最新のコメント:88888888
タグ:音楽,DTM,DTMクラシック